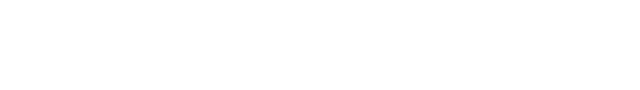鮎釣り師の独り言
最近中高年を中心に山登りがブームとなってきている。深田久弥の百名山がそれに火をつけているようでもある。私もその年齢にさしかかっているが自分の意思で山に登ろうと思ったことはまだない。しかし月に一度名水を求めて車で山越えをする。こんなところに滝があったのか、こんな身近にブナ林があるのか、新緑のころに見る青葉の美しさはたとえようのないものである。年をとるにつれて自然の中に身を置く機会が増へ、また自然を素直に感じ取ることができるようになった。現代社会は、人と自然の間に次々と垣根を作ってきているが、それに反発するかのように自然を求め、自然に回帰しているように思える。
小さい時よりテニス、卓球、ゴルフなどボールを追いかけるスポーツが好きだったので、自然に親しんだり自然を相手に何かするということがなかった。そんな私に転機が訪れたのは十五年ほど前、ガンセンターにいた頃のことで、それは鮎釣りへの誘いでした。釣りといえば、小学校のころ竹ざおで三十センチの鮒を釣った事を覚えていますが、それ以外印象に残ることはなかったようです。同室の胸部外科医と塩野義の某氏に攻め立てられついに陥落。五万円ですべての道具を揃へ、鮎の入門書を一冊読んで、これで本当に大丈夫なのか不安であったが、そんなことはお構いなしに、まず始めることが大事といざ出陣。自分の趣味に引き込むときの常道は、相手に考えさせる余裕を与えず、まず行動させることなのかもしれない。
その日はうす曇で、こんなに早くからと思う時間に集合。胸部外科医二人、大学の技士、塩野義の某氏そして私の五人。皆が集まると一言二言言葉を交わし、それぞれ車に乗って走り出す。何処へ行くとも言わず、ただついてこいという事らしい。目指すは阿賀野川の上流か。国道からそれ、民家の脇の細い道を通り、地図には載っていないような道を抜け、いつのまにか河原へ出ていた。この道は今でもよくわからない。河原に着くと皆の動きが急に早くなり、まず誰かが運んできたおとり鮎をそれぞれの囮缶に移し、それを川に活け、竿の準備をし、糸をはりそしてそれぞれ囮缶を持ってパッと散っていった。残ったのは私と塩野義の某氏だけ。川の見方、危ない場所、ハミ痕、初心者の釣りやすい場所を簡単にレクチャーして、おとり鮎に鼻管を通して「それじゃ先生がんばって」と某氏もいなくなってしまった。阿賀野川は、太く短い大河なので流量が多く変化に富み、大鮎が棲む荒瀬も多い上級者向きの河川である。いまでも怖くて一人では行かないようにしている。鮎はいっぱいいたようだが、その日は坊主(一匹も釣れないこと)。
翌日も同じメンバーで同じ場所で鮎釣り。同じ手順で始まり、違ったことは、私をいっぱしの鮎釣り師と見なしてくれたことである。昼食時に、女性二人を伴ったM氏(その当時胸部外科医)が現れ「おまえ誰だ」「小児科の太田と申します。宜しくお願いいたします」河原では新参者は仁義を切らねば受け入れてもらえないことがわかった。この日もまったく釣れない状態が続いた。鮎釣り名人と云われる大学技士氏曰く「先生よくやるね、最初はみんなそうさ」とお褒めの言葉をいただく、かといってああしろこうしろとは全く言ってくれない。これが職人の世界、うまくなりたいなら俺の技を盗めといっているようであった。鮎釣りは石についている居付き鮎の縄張りの中へおとり鮎を近づけ、それを排除しようとする鮎との絡み合いを利用した釣りです。つまり川底から三十センチ以内におとり鮎を誘導してやらなければならないのです。今思へば私のおとり鮎は川の中層から上層を吹流しのごとく泳いでいただけに過ぎません、これでは何時まで経っても釣れるわけがありません。しかし私にも幸運がめぐって来ました。おやっと思った次の瞬間,竿が下流へあっという間にのされ、支えきれず竿と一緒に川を下ることとなった。どうやって鮎を取り込んだかは定かでないが、二匹の鮎が入ったたもを抱いて河原に座り込んでいた。頭の中は真っ白、膝はガクガク、心臓はバクバク、腰が抜けた状態になっていた。生まれてはじめてこんな興奮を覚えた。そんな顛末で最初の鮎釣りが終わった。そしてまた一人鮎に魅せられた人が誕生した。毎年、解禁日が近づくにつれ胸が高鳴り、解禁前夜は興奮して眠れず、夏の間だけ漁師になりたいと夢想する有様です。
最後に私の釣りの師である開高健氏の著書「オーパー!」に載っていた中国の古い諺を紹介します。
一時間、幸せになりたかったら 酒を飲みなさい。
三日間、幸せになりたかったら 結婚しなさい。
八日間、幸せになりたっかたら 豚を殺して食べなさい。
永遠に、幸せになりたかったら 釣りを覚えなさい。
(1999.7.20 ぼんじゅーる)